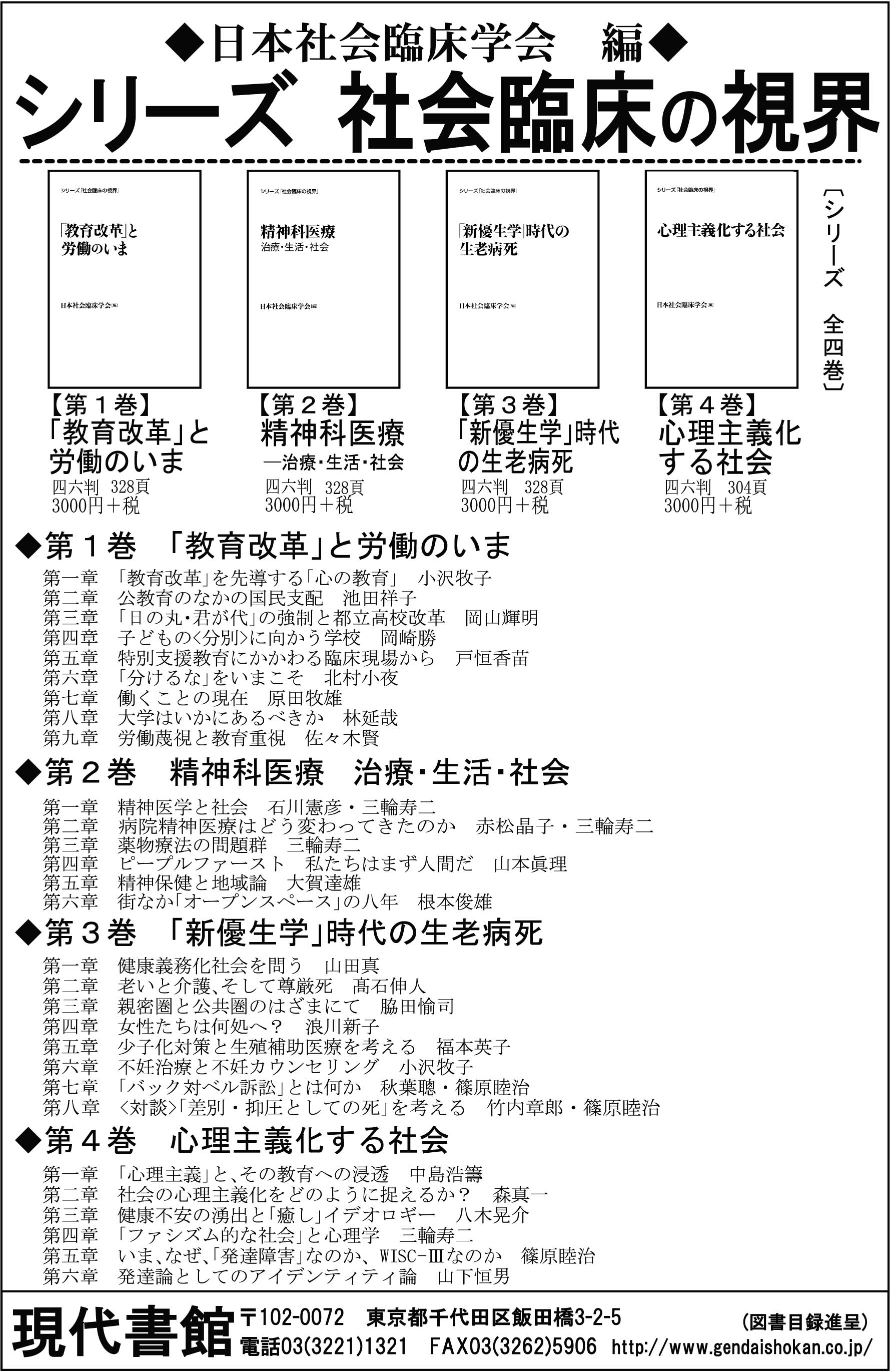第16回総会へのお誘い
世の中を良くするには社会が変わらなければならない、というのが社会臨床学会の基調の考え方だと思います。具体的な問題の原因を個人に還元することを拒み社会にその原因を見出すことを基調として心理臨床・臨床心理学を批判してきた基本的な立ち位置からは当然そのようになります。
一方で、一人ひとりの人間が変わらなければ世の中は良くならないという考え方もあります。世の中を作っているのは所詮は個々の人間なのだから、ということだけではなく、そもそも一人ひとりの人間が変わることが世の中を良くすることに繋がるのだと信じないのだとすれば、皆で集まっていろんな問題を議論することの意味等何もないからです。そこでどんな議論をしても社会が変わらなければ何も良くならないのだし、そもそも議論するとは議論の中で互いが新たな発見をし、改めて自分の考えを肯定したり、否定したり、疑問に思ったり、変質したりする機会として行われるのであって、そこに参加する個々人の変化が世の中を良くすることにつながらないのであれば、そんなことをする意味はないからです。
思想家のケン・ウィルバーは、そもそも社会と個人の間に因果関係を置くのではなく、個と集団とを別々の象限に位置づける四象限理論を提唱しました。「鶏が先か卵が先か」で議論の浪費をするよりも、ともかくも鶏も卵もなのだからそれらの全てに目を配って出来ることからやっていこうよ、という、いかにもアメリカ生まれのプラグマティックな発想がそこにはあるように思えて、僕は共感しています。今、地球上には、大から小まで、おかしなこと、危機的なことを探すのに、何の苦労もありません。個人も悪ければ社会も悪い、食べ物も悪ければ、教育も悪い、医療も悪ければ、福祉も悪い、虫歯も悪ければ、口も悪いです。手を打つのにどこが良くてどこが悪いなんてことはありません。多分、何をやっても今よりは良くなるか、せいぜい変わらないかです。良さそうなことはやってみる、あるいはヤバそうだなと思ったらせめて何もしない、踏みとどまる、そんなことを個々の人間が出来る範囲でやっていけばそれでも充分いいのではないかと思います。無理をしてもしなくてもいずれは滅びるのだから、そんな諦観もあって、そんな風に思います。
どうせ駄目なのだから、せめて、やれることをやれるだけはやっておこう、そんな風に思ったりします。
ポストモダンの季節は私達に二つの道を示してくれたと思います。ポストモダンの思想が教えてくれたように私達には多様な相対的な価値だけがあるのだとすれば、そしてその間に優劣を付けられないのだとすれば、私達は「今よりはまし」という基準に従って永遠に改善活動を繰り返す、ただしその結果「全体としてより良くなったり」は絶対にしない、永遠の循環の中を生き続ける=永劫回帰し続ける、そして何かの拍子に突拍子もないことによってその繰り返し自体が滅ぶような事態に陥って滅亡する、というような道と、私達は今よりも成長して今よりもより良い世の中を作ることが出来るのだと信じて行動する道、です。すなわち、相対的ではない、今よりもより良い状態が存在すると信じて行動する道です。どちらが正解なのかは分かりません。正解があると考えるのは後者の考え方であり、正解等そもそもないと考えるのは前者の考え方です。しかしはっきりしているのは、私達が世の中を良くしたいと考えて行動する時には、「あっちのほころびを繕えば、こっちがほころびる」という状態を当たり前と考えて、ほころびを繕い続けて、(より良くなることはないけれど)偶然発生するかもしれない「取り返しのつかない事態」だけは避け続けるべく行動し続けるのだと自覚して行動するか、人間は今よりもより良い状態に成長することが出来ると信じてその状態に成長するべく試行錯誤しているのだと自覚して行動するか、のどちらかの立場で行動しているのだし行動するしかないのだということです。そして、ふたつの考え方は根本ではまったく異なっているけれども、その都度、その時々で見るならば、具体的には同じ方向を指向し、同じ行動をしているということがしばしばでしょう。だとすれば実は、そこにはそれほどの違いなど無く、ともに歩める可能性の方が多分に大きいはずです。ポストモダンの時代は、そんなことを私達に教えてくれました。
私達は、私達が行動するために議論をしたいと思います。議論のための議論ではなく、私達が啓発され元気になれるような議論をしたいと思います。議論が殴り合いであっても励まし合いであっても、そこではそれぞれの人が元気を得られるような議論がしたいと思います(ちなみに、今回のシンポジウムのひとつでは「健康」概念を疑う議論も行われると思います。「元気」などという言葉も、もしかしたら問うべき言葉のひとつかもしれませんが、でもやっぱり「元気」という言葉は、僕にはリアルな言葉です)。
今回、運営委員会内の輪番で僕が総会実行委員長を担当します。名ばかりで実際には他の運営委員などの方々のお世話・力で実行できているのですが、今回実行委員長をやっている人間がどのような人間なのかという自己紹介がてら、この巻頭言を書かせていただいています。
第16回総会の、ご参加の皆さん全員が楽しんで過ごしていただけることを願っています。